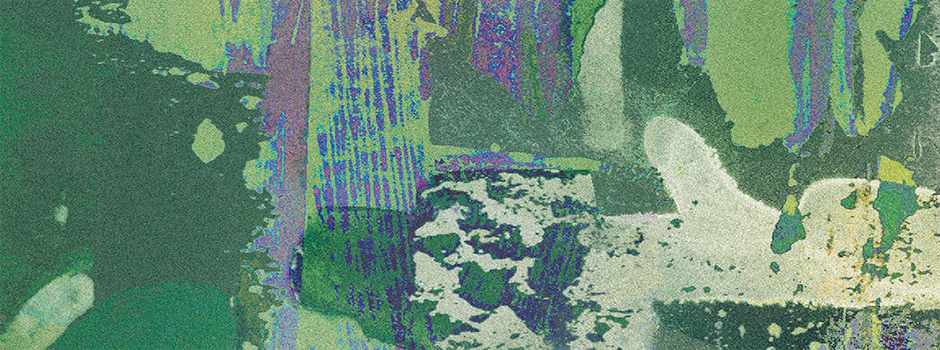ホーム > 原研究室について
「Interior Music - Cafe Apres-midi meets ACME Furniture」by 藤田二郎(FJD, Instagram)
研究室の概要
ミッション
早稲田大学人間科学部・早稲田大学大学院人間科学研究科は、ミッションのひとつとして「持続可能な社会の構築に貢献する教育・研究に取り組む」ことを掲げています。持続可能な社会の構築を目指すうえで重要な課題となるのが、「開発」をめぐる諸問題です。周知のように、現在世界各地で「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)」の実現に向けた取り組みが進められています。
私たちの研究室では、「開発」を「人間が、みずからの目的を達成すべく、〈環境〉に意図的に働きかける集合的な営み」と広く捉えたうえで、人類学の立場から「開発」に関する研究に取り組んでいます(※「開発」の様々な定義についてはこちらをご覧ください)。ここでいう〈環境〉には、自然環境だけでなく、社会文化的な環境も含まれます。
人類学とは、一言でいえば、「文化」に強く依存する生物種としての人間集団の多様性/共通性、その変化、集団間の関係などを明らかにすることを通して、人間とは何かについて考える学問です。
私たち人間(Homo sapiens)は、今から約20万年前にアフリカ大陸に出現し、その後、地球上の広範な地域にその生息域を広げてきました。そしてその過程で、「故郷」であるアフリカとは大きく異なる自然環境にも適応してきました。人間は、文化に強く依存しつつ、多様な文化を創り上げる力を有していたからこそ、多様な自然環境に適応できたのだといえます。人間は、地球を自然環境と文化環境が複雑に絡み合った世界へと「開発」し、そうした世界のなかでみずからを形成してきた「ナルチュラル(natural-cultural)」な存在なのです。
人類学の大きな特徴は、このような人類史的な視野のもとで現代を捉え直し、グローバルな社会とローカルな社会の双方を視野に入れる複眼性を有している点にあります。また、調査・研究の方法として、特定の地域や集団を対象にした「エスノグラフィー」と、複数の地域や集団を対象にした「比較研究」を重視している点も大きな特徴です。
人間科学部・人間科学研究科では、学際性・総合性を重視していますが、人類学はそれ自体が学際性・総合性という性格を有する学問なのです。
私たちの研究室では、以上のような人類学の特徴をふまえつつ、持続可能な開発をめぐる課題の発見と解決をめざすエスノグラフィーの作成、既存のエスノグラフィック・データを活用した比較研究、そして持続可能な開発において「文化」の視点を重視する「文化的持続可能性」に関する事例研究・理論的研究を進めています。
主な活動
- 個人研究
- メンバー各自が個人研究に取り組み、その成果を論文にまとめるとともに研究発表を行ないます。
- 文献講読
- 日本語・英語の文献講読とディスカッションを通じて、人類学や開発に関する基礎知識と文献の多読・精読のスキルを身につけます。
- 調査実習
- 日本国内の特定の地域を対象にした短期の調査実習を実施します。実習を通して、現地調査に取り組む上で必要となるスキルやマナーを実践的に学びます。
- 交流イベント
- 研究室内でのコンパや合宿だけでなく、他大学の研究室との交流イベントも開催します。
基本方針
私たちの研究室では、以上に挙げた活動に取り組むことを通して、研究室のメンバーひとりひとりが、早稲田大学人間科学部および人間科学研究科のディプロマ・ポリシー(DP)に掲げられている能力に磨きをかけ、「自立」できるようになることを目指します(人間科学部DP/人間科学研究科DP)。
ここでいう「自立」とは、単に「経済的自立」というだけでなく、「知的自立」「精神的自立」「社会的自立」ということを含んでいます。経済的自立はわかりやすいと思いますが、そのほかの「自立」について簡単に説明すると、以下のようになります。
- 知的自立…… (卒業研究の経験を経た後に)独力で人類学的な研究のプロジェクトを計画・実践できること
- 精神的自立…… 「自分がこうなったのは家族のせい、学校のせい、世の中のせい」などと「他人のせい」にしないこと
- 社会的自立…… 自分とは考え方や価値観が異なる人びとと協働できること
私たちの研究室では、メンバー各自が、このような多面的な「自立」とそれに向けた成長を意識し、卒業後の人生をみずからの力で切り開いていくことができるようになることを目指しています。
その際に私たちの研究室で重視するのは、「みずから学ぶ」「互いに学び合う」「失敗から学ぶ」ということです。
みずから学ぶ
「誰かに言われたから」と他律的に学ぶことは知的自立からはほど遠いですし、他律的に学んだことよりも、みずから学んでつかみとったことの方が身につきます。「自律」的な学びは、知的自立の必要条件であると同時に、人間科学部DPに掲げられている以下の「自己教育」に直結するものです。
- 自律性・積極性・協調性を備え、自己教育をおこなうことができる
- みずからのキャリア・プランをデザインすることができる
「みずから学ぶ」ことを重んじるということはまた、メンバー各自の自主性と選択を尊重するということでもあります。たとえば、私たちの研究室では、研究室を運営する上で必要な役割を各メンバーに担ってもらいますが、その役割はけっして固定的なものではありません。各メンバーが状況を判断して、状況に柔軟に対応しながら自主的に行動することを重視しています。このことは、研究室でおこなう調査実習にも当てはまります。
また、研究室で実施する調査実習は原則全員参加となりますが、その他の交流イベントへの参加は、強制ではありません。ただ、参加することを選択した以上は、参加者ひとりひとりが、それなりの責任を担うというのが、私たちの研究室の方針です。
互いに学び合う
毎週ゼミをおこなうのは、単に教員や文献から知識を得るためではなく、各メンバーがみずから学んだ成果を他のメンバーと共有して、互いに学び合うためです。調査実習や交流イベントではグループワークが中心になりますし、文献講読においても互いに学び合うことを重視しています。互いに学び合うために、私たちの研究室では、以下の3点を心がけています。
- 誰もが安心して自由に意見を述べることができる場をつくること
- 他のメンバーの意見にしっかりと耳を傾けること
- 他のメンバーが受け入れられるように異論を述べること
「互いに学び合う」とは、お互いを尊重しつつ、高め合うことです。とはいえ、それを実践するのは容易なことではありません。うまくいかない場合もあるでしょう。だからこそ、次に述べる「失敗から学ぶ」ということが重要になります。
失敗から学ぶ
研究を進めるプロセスでは、小さなことから大きなことまで、さまざまな失敗を経験するものです。もちろん、致命的な失敗は極力避ける必要があります。ただ、致命的でない失敗であれば、それは、とても大切な気づきと学びの機会になりえます。
失敗の経験を通じて身に沁みて学んだことは、学生時代のもっとも貴重な財産といっても過言ではありません。だから失敗を恐れる必要はありません。
大切なのは、失敗の経験を適当に受け流すことなく、それと向き合うこと、失敗を他人のせいにしないこと、そして同じ失敗をできるだけ繰り返さないように工夫することです。
「みずから学ぶ」「互いに学び合う」「失敗から学ぶ」という3つの学びがかみ合ってこそ、多面的な「自立」を遂げることができると私たちは考えています。
よくある質問
-
研究室・ゼミ室はどこですか。オフィスアワーも教えてください。

-
研究室は100号館5階のE538室、ゼミ室(実験室)は同じく100号館5階のE553室です。オフィスアワーは月曜日の12:20-12:50です。オフィスアワーでの面談を希望される場合は、事前にWasedaメールからご連絡ください。

-
 エスノグラフィーは現地調査重視なので、文献資料や統計資料はあまり扱わないと考えてよいでしょうか。
エスノグラフィーは現地調査重視なので、文献資料や統計資料はあまり扱わないと考えてよいでしょうか。
-
 文献資料や統計資料も扱います。現地調査をする前に、まず、文献資料や統計資料を読み込むによって、すでに明らかになっている事実や他の研究者によって論じられていることを把握しておくことは重要です。また、現地でしか手に入らないような文献資料や統計資料を入手することも、現地調査の目的のひとつとなります。
文献資料や統計資料も扱います。現地調査をする前に、まず、文献資料や統計資料を読み込むによって、すでに明らかになっている事実や他の研究者によって論じられていることを把握しておくことは重要です。また、現地でしか手に入らないような文献資料や統計資料を入手することも、現地調査の目的のひとつとなります。
-
 ゼミに関連する科目を教えてください。
ゼミに関連する科目を教えてください。
-
 関連科目は以下のとおりです。本ゼミを希望する方は、履修することをおすすめします(【指定】=指定科目)。
関連科目は以下のとおりです。本ゼミを希望する方は、履修することをおすすめします(【指定】=指定科目)。
- 教養科目(A:2単位以上、B~G:6単位以上):グローバリゼーション論(E)【指定】、自然人類学(A)、進化論(A)、哲学(A)、社会科学の理論(C)、NPO/NGO論(G)
- 実調科目(6単位以上):参与観察法【指定】、インタビュー調査法
- 基盤科目(6単位以上):文化人類学【指定】、歴史学、考古学、人口学、社会学
- 発展科目(32単位以上):環境人類学【指定】、環境民俗学【指定】、社会開発論【指定】、歴史人類学、史学方法論、環境史、経済人類学、環境社会学、都市社会学、国際社会学、社会調査論、経済学、環境経済学、地域資源論、日本民俗学、アジア地域研究、アメリカ地域研究、ヨーロッパ地域研究、世界地誌学、基礎生態学
- 人類の進化について学ぶ:進化論、自然人類学
- 文化人類学の基礎知識と下位領域について学ぶ:文化人類学、環境人類学、歴史人類学、経済人類学
- 文化人類学の方法について学ぶ:参与観察法、インタビュー調査法、社会調査論
- 世界各地の地域文化について学ぶ:アジア地域研究、アメリカ地域研究、ヨーロッパ地域研究、世界地誌学
- 現代世界における「開発」をめぐる諸問題について学ぶ:グローバリゼーション論、NPO/NGO論、社会開発論
- 隣接分野について学ぶ:哲学、社会科学の理論、歴史学、考古学、人口学、社会学、日本民俗学、環境民俗学、史学方法論、環境史、環境社会学、都市社会学、国際社会学、経済学、環境経済学、地域資源論、基礎生態学
-
 ゼミの先輩たちはどんな研究テーマに取り組んでいるのでしょうか。
ゼミの先輩たちはどんな研究テーマに取り組んでいるのでしょうか。
-
 ゼミ生のみなさんは、持続可能性や文化を考慮した地域づくりという枠組みのなかで各自がテーマを設定して研究に取り組んでいます。研究テーマの具体例としては「エシカル消費の視点から考える地域開発」「ソーシャルメディアを活用した地域活性化」「持続可能な祭りの運営方法」「伝統的建造物を生かしたまちづくり」「スポーツツーリズムによる地方創生」「日本遺産と持続可能な観光」などが挙げられます。こちらのページもご参照ください。
ゼミ生のみなさんは、持続可能性や文化を考慮した地域づくりという枠組みのなかで各自がテーマを設定して研究に取り組んでいます。研究テーマの具体例としては「エシカル消費の視点から考える地域開発」「ソーシャルメディアを活用した地域活性化」「持続可能な祭りの運営方法」「伝統的建造物を生かしたまちづくり」「スポーツツーリズムによる地方創生」「日本遺産と持続可能な観光」などが挙げられます。こちらのページもご参照ください。
-
 通常の授業以外にどのような活動がありますか?
通常の授業以外にどのような活動がありますか?
-
 短期の調査実習、日帰りフィールドトリップ、慶應義塾大学・上智大学との合同ゼミ、ゼミ合宿、ゼミコンパ、ランチミーティングなどの活動を行なっています。
短期の調査実習、日帰りフィールドトリップ、慶應義塾大学・上智大学との合同ゼミ、ゼミ合宿、ゼミコンパ、ランチミーティングなどの活動を行なっています。
学生の声
学生の声 vol.1
こんにちは。原ゼミのHPへようこそ! 私からは人間科学部で学べることやゼミの活動について紹介します。
人間科学部は多様性に富んだ学問がそろっています。私自身は心理学が学びたいという理由から人間科学部に進学しました。入学してから、心理学はもちろんのこと建築学や情報学、環境学など様々な領域へ学びの場を広げることができました。それぞれの領域での学びを掛け合わせて新しい発見や自分なりの考えを持てることが人間科学部の魅力だと考えています。自分の興味に合わせて授業をカスタマイズし、多角的な視点を身につけることができます。
原ゼミでは「持続可能な開発、地域づくり」をテーマとして研究を進めています。その中でも、ゼミ全体で取り組む共同研究と一人一人でテーマを決める個人研究があります。
共同研究では、夏休み期間中に沖縄の石垣島へフィールドワークへ行き、地元の方々や観光客、市役所の方々にインタビューを行ってきました。特に地元の方々と近い距離でコミュニケーションを取り、生の意見を伺ったことで発見した観光における課題や将来性についてチームでまとめました。学内でゼミ活動で学んできたことを、学外で実践できる機会は自分にとって大きな成長の場となりました。さらに、共同研究の成果を3大学合同報告会で慶應義塾大学・上智大学のみなさんと共有したことで、学びの輪を広げることができました。
個人研究では「住民の主体性と持続可能なまちづくりの関連性」について研究しています。開発側が一方的に行うまちづくりではなく、住民参加型のまちづくりを実現するために必要な要素やメリットについて調査を進めています。ゼミのメンバーはそれぞれ異なったテーマで個人研究を進めていますが、お互いの研究発表から学べることも多く、刺激をもらえます。
ゼミ活動を通して感じていることは、ゼミで学んだことが確実に他の場面でも活きているということです。ゼミで読んだ文献や石垣島でのフィールドワークから得た知識は自分の財産となっています。また、これらの活動に高いモチベーションを持って一緒に取り組める仲間がいることも原ゼミの魅力です。主体的に学びたい、切磋琢磨しあえる仲間を作りたい方は、ぜひ原ゼミにいらしてください。
(NAGAYAMA Riko)
学生の声 vol.2
私たちの研究室のホームページをご覧いただきありがとうございます。当ゼミの主な研究テーマは「持続可能な地域づくり」であり、このテーマに沿って日々研究活動に取り組んでいます。ここでは、ゼミの活動をご紹介しながら、私が感じた当ゼミの面白さについてお伝えしたいと思います。
まずは、当ゼミにおける長期プロジェクトへの取り組みについてご紹介します。当ゼミでは、「調査実習」と「卒業研究」に向けて日々取り組んでいます。一つ目の調査実習では、夏休み期間中に沖縄県・竹富島でフィールドワークを行い、竹富島の地域づくりとリゾート開発について学びました。この活動を通して、チームでプロジェクトに取り組むという経験ができました。全員で一つのテーマについてアイデアを出し合い、役割分担をしながらゴールを目指すプロセスは、困難もありましたが非常に達成感がありました。二つ目の卒業研究では、持続可能な地域づくりという軸に沿って各学生が関心のあるテーマに取り組んでいます。自分の関心のあるテーマについて、自分の力で問題設定を行って追究し、それに対する主張を組み立てていくことは重要な経験であると感じます。
次に、ゼミを通した学生同士の交流についてご紹介します。当ゼミでは、学内外の様々な学生と交流ができます。普段のゼミの中では、様々な地域・高校から早稲田大学に入学してきたゼミ生と出会い、それぞれ違った興味関心を持つ人と活動します。多様なバックグラウンドを持つ人と共に活動ができる経験は社会に出ても大いに役立つと思います。また、当ゼミの特色として、他大学の学生との交流も挙げられます。先にご紹介した調査実習の成果発表は、早稲田・慶應・上智の3大学合同の報告会で行いました。同じ研究領域に取り組む学生同士の交流は、お互いに成長できる有意義な経験でした。
このように、当ゼミでは将来に役立つ経験ができます。一つのプロジェクトに時間をかけて取り組み、その過程で仲間と協働した経験は将来大いに役立つでしょう。ゼミ活動を通して、専門分野についての知識を深め、問題解決を目指し、主体的に学ぶことができます。このような総合的な「学び」を体感できる場が、当ゼミにはあります。当ゼミでは、地域づくりに関心を持ち、様々な経験にチャレンジしたい学生をお待ちしています。
(TAKAHASHI Kazuaki)
学生の声 vol.3
私が人科を志望したのは、自分の実家のある沖縄・石垣島にたくさんの伝統文化や年中行事が根付いていて、大学では文化人類学を学びたいと思っていたからでした。そこで、幼い頃から憧れていた早稲田大学で、文化人類学を専攻している先生方が多い人科に魅力を感じて受験することを決めました。
人科のカリキュラムでは、幅広い領域の学問を学べることに魅力を感じます。実際に3年生からゼミが始まり、自分の研究テーマのことを考えるようになってくると、以前から学びたいと思っていた文化人類学と並行して、教育関連分野にも興味が出てきました。1年生の頃に教育インターンシップの授業を通して、半年間、所沢市の小学校を訪問させて頂いた経験があり、その時の学びが現在取り組んでいる研究テーマにも生きています。教職関連科目を履修していたこともあるため、今後は開発人類学と教育を結びつけて、卒業研究に生かしていきたいと考えています。
人科では、他学科の授業を履修したり、様々なプロジェクトに関わることができるので、とても嬉しいです。様々な学問領域に対して深く広く研究していらっしゃる先生方が多く在籍しているだけでなく、学生が全く異なる専門分野に興味を持ったときにも、自身の意欲さえあればどれだけでも学びを得る機会があるところが人科の魅力だと感じています。
また、私は早稲田大学の給付型奨学金「目指せ!都の西北奨学金」を受給させていただいているので、年に一回稲門祭でスタッフをする機会があります。1年生の頃にkidsコーナーを担当させて頂いた際、お世話になった校友会の方々やボランティアの方々と仲良くなることができて、今でもその交流は続いています。kidsコーナーでは、子どもと関わることが自分にとってどれだけ大事な軸であるのかを毎年考えさせられるため、私の早稲田での経験として、とても自慢できる素敵な時間です。年に一度の稲門祭スタッフですが、奨学金を受給していることで、さらに早大生としての自覚や自身の考え方もしっかり持とう、という意識を強く持ち続けることが出来て、奨学生であることを誇りに思っています。
ゼミでは実際に調査をする現地へ赴いて、そこに暮らす人々との交流を通して座学だけでは感じることのできない学びを得ることができます。また、自分の興味のある分野についてある程度知識を蓄えた上で他の学生と話し合えることが、より建設的な学習のスタイルにつながり、とても良いと思います。
さらに原ゼミでは、ゼミ活動を通して自分と同じ興味を持つ、あるいは学ぶことに高い意識を持つ学生と交流することが出来て、常に活気のある雰囲気があります。学習と日常生活のメリハリをつけて、一人ひとりが自分の目標に向かって努力を怠らないだけでなく、他メンバーの将来に対しても同期、先輩、先生が一丸となって考えてくれる暖かい人が大勢在籍しているゼミです。「様々なことを積極的に学んで吸収したい!」と感じている高校生や後輩の皆さん、ぜひ原ゼミにいらしてください。お待ちしています!
(DAIKU Hidemi)
「開発」とは何か
「開発」の様々な定義
- 「開発とは、地球上のあらゆる地域の人々が自分たちの生存の可能性を拡張するための行為である」(菊池編 2001: 3-4)
- 「開発とは、人々の暮らしや社会の仕組みを望ましい方向に導く試みといえる」(菊池編 2001: 100)
- 「〔開発とは〕社会や社会システム全体を『より良い』『より人間的』な生活に向けて持続的に向上させていくこと」(トダロ&スミス 2010: 27)
- 「『環境』とは私達の住むところであり、『開発』とはその中で私達の生活をよくするよう努力することです」(環境と開発に関する世界委員会編 1987: 6)
- 「〔開発とは〕人間の必要事項を満たし人間生活の質を改善するための生物圏の改良と、人的、財政的、生物的および非生物的資源の利用〔のこと〕」(国際自然保護連合 1980: 25)
- 「開発――人間のニーズを満たし、人間生活を質的に向上させること――の成否は自然保全に左右される」(アレン 1982: iv)
- 「開発の定義はさまざまであるが、改良(improvement)、エンパワーメント(empowerment)、参加(participation)は、ほとんどの定義においてキーワードとなっている。(改行)改良とは、現地の人々が理解し、受けいれ、価値あるものと認識する事柄に対する改善(betterment)をさす。エンパワーメントとは、改良に関わる変化を計画立案やマネージメントするための力を現地住民につけさせることを意味する。参加とは、社会の異なるメンバー(集団、下位集団)が現在と将来において彼らの生活に影響を与える決定に関与することを意味する」(ノラン 2007: 21)
- 「開発の基本的な目標は人々の選択肢を拡大することである。これらの選択肢は原則として、無限に存在し、また移ろいゆくものである。人は時に、所得や成長率のように即時的・同時的に表れることのない成果、つまり、知識へのアクセスの拡大、栄養状態や医療サービスの向上、生計の安定、犯罪や身体的な暴力からの安全の確保、十分な余暇、政治的・文化的自由や地域社会の活動への参加意識などに価値を見出す。開発の目的とは、人々が、長寿で、健康かつ創造的な人生を享受するための環境を創造することなのである」(国連開発計画)
- 「開発をどう理解したらよいだろうか。もし、開発を、国民の生活改善をもたらす経済的社会的近代化の過程と考えるならば、厚生(wellbeing)の定義は何だろうか。これまで現れた多くの哲学的研究――アリストテレスやウパニシャッドに始まる――からは、厚生に関して、三つのアプローチを区別することができる。楽しい生活(pleasant life)、良い生活(good life)、意味ある生活(meaningful life)、の三つである」(西川ほか編 2011: 63)
- 「developmentは、成長や進化、成熟といった、ともに形成されてきた言葉とのつながりを絶つことができない。まったく同様に、いまこの言葉を使う者は、思想、行動を歪める意味の罠から免れることができない。それがどのような文脈で使われようと、使う者が言おうとした本当の意味が何であろうと、この表現は、意図とは反対の意味に受けとられ、色づけされるだろう。この言葉はつねに好ましい変化を暗示し、単純なありようから複雑なありようへの一歩、劣悪な状態からよりよい状態への一歩を匂わせる。普遍的、必然的な法則に従い望ましい目標に向かって前進しているのだから、問題はないのだとほのめかす。(中略)だが、development――それを指向する社会構造が二世紀にわたって続いたために、根強い信仰となってしまったが――の現実の意味は世界の三分の二の人びとに、自分たちが何であって何でないかを痛烈に思い出させる。それは自らの忌むべき惨憺たる状態を思い出させる。その状態から逃れるには、この人びとは他者の経験と夢のとりこにならざるをえないのである」(ザックス編 1996: 24)
- 「こうした語のもつれを見ていくと、『開発途上(developing)国への援助』という、たいていは度量の広い意図が、他者を『低開発(underdeveloped)』とか『遅開発(less developled)と定義することによって、そのアイデンティティを抹殺したり、開発(development)の過程を押しつけることによって、外部の者の支配する世界市場に奉仕させるという、まったく度量の狭い行動とからんでいることがよくわかる」(ウィリアムズ 2011: 167-168)
参照文献
- アレン, R. 1982『世界環境保全戦略――自然と開発の調和をめざして』竹内均訳、日本生産性本部。
- ウィリアムズ, R. 2011『完訳キーワード辞典』椎名美智ほか訳、平凡社。
- 環境と開発に関する世界委員会編 1987『地球の未来を守るために』福武書店。
- 菊池京子編 2001『開発学を学ぶ人のために』世界思想社。
- 国際自然保護連合 1980『世界自然資源保全戦略』環境庁自然保護局調整課。
- ザックス, W.編 1996『脱「開発」の時代──現代社会を解読するキイワード辞典』三浦清隆ほか訳、晶文社。
- トダロ, M. P. & S.C. スミス 2010『トダロとスミスの開発経済学』森杉壽芳監訳、ピアソン桐原。
- 西川潤ほか編 2011『開発を問い直す――転換する世界と日本の国際協力』日本評論社。
- ノラン, R. 2007『開発人類学――基本と実践』関根久雄ほか訳、古今書院。